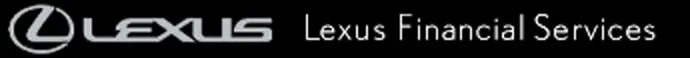森に宿る歴史と文化に触れ、そこに息づく生命に触れる
LEXUSで巡る「鎮守の森」〜サステナビリティを考える旅。伊勢神宮「宮域林」篇
日本の国土のおよそ3分の2を占める森林。豊かな緑が守られてきた背景には、「鎮守の森」としてこれを保護してきた神社の存在がある。日本のものづくり精神の粋を結集してつくられるLEXUSに乗って、これらの森を訪れ、日本人が大切にしてきた「自然との共生」について考え直してみないか。
Text & Photo:Shigekazu Ohno(lefthands)
100年先、1000年先の、環境のあるべき姿を考える
鎮守の森は、八百万の神々を祀る神道において、社だけでなく、その土地全体が神域であるという考え方のもとに大切に守られてきた。神域であるがゆえに樹木の伐採や動物の狩猟が禁じられてきたことから、そこには生態系豊かな、あるべき原初の自然の姿が残されている。
再生可能エネルギーで走るLEXUSのBEVなら、この貴重にして神聖な「鎮守の森」を訪ねても、空気や水を汚すことがない。そこから見える景色に重ねて、100年先、1000年先の、環境のあるべき姿を考えてみてはどうだろう。
今回は、伊勢神宮が歴史を通じて大切に守り育ててきた宮域林(きゅういきりん)を訪れ、そこに息づく神話と、多様な生命との出会いを求めた。
伊勢神宮の鎮守の森「宮域林」


天照大御神が身を隠したとされる「天の岩戸」伝説。そこから流れだした湧水はやがて谷を下り、五十鈴川となって伊勢神宮の鎮守の森「宮域林」を育て、伊勢神宮の神域である宇治橋のたもとでは、参拝する者たちの身を清めてきた。川は下るにつれて水量を増やし、幅を広げ、田畑を潤した末に伊勢湾へと辿りつき、カキやタイ、真珠といった海の豊穣を人びとにもたらした。

そうした生命の水に育まれた「宮域林」は、面積がおよそ5,500ヘクタール。プロ野球のスタジアム約1,100個分といえば、そのスケールの大きさに思いをいたすことができるだろうか。山に登って見下ろすと、まさに目路の限りに広がる鬱蒼とした森であることが見てとれる。
伊勢神宮は、神話においては天照大御神の御鎮座地である。その悠久の歴史を通じて、常若(とこわか)の思想から20年に一度、社殿をはじめ、すべての建物や神具を新しくして、大御神に新宮へお遷りいただくお祭りとしての式年遷宮が執り行われてきた。そしてそのために、100年以上もの昔から、神事として大切に森が手入れされてきた。

木を切り、そこにまた新たな木を植え、御造営用材となるまで、およそ200年かけて育てる――というのが、「サステナビリティ」という言葉が使われるようになるはるか以前から、伊勢神宮が実践してきたことだ。かつての森がそうであったように、健全なヒノキ材を育てるために、ヒノキ以外の植生もありのままの姿で大切に守ってきた結果、この森には地を這う生き物から空を飛ぶ生き物まで、多種多様な生態系が保たれている。

鳥のさえずりに耳を傾け、草花の匂いを嗅ぎ、ときに急峻な岩肌を伝って森を歩いてみる。こずえの影からちらちらとこちらをうかがうのは、声も形もかわいらしいヤマガラとシジュウカラ。湧水を見つけてそっとのぞいてみると、透明な水の底にはアカハライモリが何匹もいて、じっと身を潜めている。せせらぎの音に誘われて沢に下りると、鮮やかな紅色が目を奪うサワガニもいた。みんな、愛すべき森の小さな住人たちだ。



彼らとの出会いから、木や石や水といった万物の中に神を見る神道が、実はその信仰によって人びとを庇護してきたのと同様に、人以外の生命も守ってきたのだと知り、幸福感に浸る思いがする。資料によると、この宮域林には動物約2,800種、鳥類約140種、植物約850種が確認されているという。この豊かな生態系を含めての、神の森なのだろう。

人以外の生き物も、伊勢神宮とともに、これからもこの地でずっと尊い命をつないでいけるように――。もしも伊勢神宮をお参りする機会に恵まれることがあったら、その後ろに広がる森を見上げ、私たち一人ひとりができることを、今一度考えてみないか。
伊勢神宮・宮域林
| 伊勢神宮の参拝時間: | 1月・2月・3月・4月・9月:午前5時~午後6時 5月・6月・7月・8月:午前5時~午後7時 10月・11月・12月:午前5時~午後5時 |
| 伊勢自動車道・伊勢西I.C.から約10分 | |
| 駐車場: | あり(伊勢神宮内宮参拝者向け・市営宇治駐車場) |