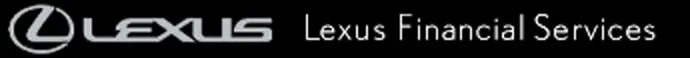地球環境を考える
ハワイが世界を牽引する。100年先へつなぐ持続可能な観光地の取り組み
美しいビーチやアロハスピリットで人びとを魅了してきたハワイ。2014年から「アロハプラスチャレンジ」を掲げ、今世界で考えられているSDGs17項目発表よりも前に、持続可能な未来を実現するためのゴール目標を設定した州でもある。オーバーツーリズムの課題解決に向けて訪れる人と住民がともに満足できる未来を目指す取り組みの背景や、コロナ後にあらたに設定した観光戦略を紹介する。
Edit&Text:Misa Yamaji(B.EAT)
ハワイ版のSDGs「アロハプラスチャレンジ」とは
世界中から観光客が訪れる、世界有数のリゾート地・ハワイ。人気の理由は、美しいビーチや温暖な気候、そして人びとを惹きつけるアロハスピリットなど挙げればキリがないだろう。しかし、そんなハワイも歴史の中で文化の消失危機、オーバーツーリズムと、ハワイの美しさを脅かす出来事に直面してきた。

今や日本をはじめ、観光立国でも問題になっていることだが、ハワイは50年以上も前から、こうした問題に向き合い、州をあげて独自の取り組みをしてきた。
例えば、国連がSDGsの目標を発表した2015年より前の2014年に、ハワイ州独自の持続可能な社会目標「アロハプラスチャレンジ」を設定。官民一致団結しながら文化を守り、経済とくらしのバランスをとり、土地の持つ“美しさ”を未来につなげていく努力をしている。

観光立国としてのジレンマをどう捉えているのか。ハワイ州観光局 日本支局のミツエ・ヴァーレイ氏に今の取り組みについてインタビューした。

――まず、「アロハプラスチャレンジ」とは、どんなものなのか教えていただけますか?
ミツエ氏:2011年にハワイで開催されたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が契機となって生まれた、ハワイ州独自の持続可能な社会の実現に向けて進める社会目標です。2030年までに、1. クリーンエネルギーへの転換 2. 固形廃棄物の削減 3. 地元産の食材供給 4. 天然資源の管理 5. スマートで持続可能なコミュニティ 6. グリーンジョブおよび環境教育という6つの目標を掲げています。

――国連がSDGsを発表したのは2015年。それよりも先にこうした目標値を掲げる、という背景にはどういったことがあったのでしょうか?
ミツエ氏:今では世界でも浸透してきた“レスポンシブル・ツーリズム”という考え方ですが、ハワイ州ではかなり前から自然に根付いた考え方でした。遡れば、環境保全という概念よりも前に、ハワイ独自の文化を守るという1976年に提唱された“Mālama Hawaiʻi マラマハワイ”という、考え方に至ると思います。
――“マラマハワイ”とはどんな考え方ですか?
ミツエ氏:マラマハワイはハワイ語で、直訳すれば“ハワイを思いやる心”という意味です。
1960年代後半から1970年代にかけて、ハワイでは「ハワイアン・ルネッサンス」と呼ばれる文化復興運動が起こっていました。これは、ハワイの文化が失われる危機感から生まれた運動であり、ハワイ語の復興、伝統的な航海術の再興などを通じて、アイデンティティの再構築を目指したものです。特に1976年のポリネシア伝統航海カヌー「ホクレア号」航海の成功は、ハワイ文化の復興を象徴する出来事となりました。さらに、1978年にはハワイ語が公用語に復活し、ハワイ語で教育を行う学校も開設されるようになりました。

加えてハワイは、日本と同じく“万物に神が宿る”と考える自然信仰ですから、環境を守ることが文化継承と直結している。この古くから浸透している考え方が、持続可能な観光の必要性を住人が自然に感じることにつながっているのだと思います。
――こうした目標を達成するために、具体的にはどんな取り組みをされていますか?
ミツエ氏:企業や学校で、観光や文化、環境保全に向けた教育などを行い、草の根運動からの意識づけを大切にしています。そのうえで観光業のリーダーや企業が、自ら州全体を挙げて目標に取り組んでいくのかを考えていただいています。
――具体的に皆さんどう落とし込まれているのでしょうか?
ミツエ氏:例えば身近なところでは資源の問題。ホテルでアメニティ類からプラスチックを排除する、というのはすでに浸透していますね。ほかにも客室に持ち歩き可能なウォータージャーを入れて、館内のウォーターサーバーで水を入れて持ち運べるようにし、ペットボトルの水を購入して持ち歩かなくてもよいような取り組みをされているところもあります。

――観光客が意識することなく、資源のロスに関われるのがいいですね。
ミツエ氏:そうですね。バケーションはリフレッシュですから、“こうしなければならない”という押し付けにならない伝え方は工夫をしています。
資源のロス、ということだけではありません。例えば日焼け止めなども、環境に負荷を与えないミネラルだけで構成されたものをショップが積極的に売れば、自然と観光客の方はそれを選んでくださる。ほかにも、たいていのホテルにはカルチャーアドバイザーというゲストにハワイの文化の大切さ、礼儀や習慣についてレクチャーする人が常駐しており、ハワイらしい体験をしたいと思うゲストに対してハワイの文化にふれるタッチポイントをつくる仕組みがあります。

© HTA / Ben Ono

© HTA / Ben Ono
――観光客が多くなると、環境保全は難しいですよね。コロナ禍を経て、その前のオーバーツーリズムを見直すという動きがあるということを聞きました。
ミツエ氏:コロナ禍の前、2019年はハワイへの年間観光客数が1,000万人を突破し、観光産業への依存度がさらに高まった年でした。140万人の人口に対し、観光客の数が7倍となり、観光産業の恩恵だけでなく負の側面が目立ち始めた時期でもあります。住民の観光業への満足度が低下し、特に観光客の多い地域では生活環境への影響が懸念されるようになりました。
コロナ禍によって観光客の数が激減し、ハワイの自然環境が劇的に回復しました。この経験は、持続可能な観光への意識をさらに高める契機となったのは間違いありません。
――海がきれいになったというのはニュースで見ました。
ミツエ氏:そうですね。特に年配の方々は、かつての美しいワイキキを思い出したようでした。静かになったワイキキビーチではハワイアンモンクシールが子どもを産んだと話題にもなりました。こうしたことを経て、観光と環境保全の両立を住人レベルからの意見を吸い上げるというコミュニティミーティングが活発化しました。

――具体的にはどんな変化がありましたか?
ミツエ氏:例えば、2021年にはハワイ州はハナウマ湾自然保護区の入場者数を従来の4分の1となる1日1,400人に制限。オンライン予約も導入し、休業日は週3日に増やし、入場料もこれまでの12ドルから25ドルに値上げしました。ダイヤモンドヘッド州立記念碑の入場も事前にオンライン予約が必要になり、入場料は5ドルに値上げしました。
値上げしたその料金は、環境教育や自然保護区のメンテナンスなどに直接投入されています。

――宿泊税も9.25%から13.25%(10.25%+市郡3%)に増税されましたね。
ミツエ氏:そうですね。観光地としての持続性を確保するため、観光誘致のマーケティング予算や一般財源投下による各州機関プロジェクトへのサポートのみならず、地域コミュニティの観光業への参画を促すプログラムや仕組みが必要でした。この宿泊税の増収分は、環境保護や地域の社会インフラ維持、自然保護区域の維持や、ハワイ先住民の文化継承プログラム、さらには持続可能な観光の啓発活動などに活用されています。
――こうした施策から観光客が減るという懸念はなかったのでしょうか?
ミツエ氏:経済を回すことも大切ですが、くらしている住民の満足度も非常に大切。ホスピタリティには地元住民の関わりが大変重要となります。観光客数を単に増やすのではなく、「質の高い観光体験」と「環境と文化の保護」の両立を目指しています。ハワイ州では、年2回の住民満足度調査を実施し、観光業が地域社会にどのような影響を与えているかをモニタリングしています。調査結果を基に、持続可能な観光政策を立案し、観光客と住民のバランスを保つ取り組みを進めています。
――これは日本のオーバーツーリズムの状況にも参考になりそうな施策ですね。
ミツエ氏:観光業は、地域社会や自然環境と調和しながら発展するべきものです。旅行者にも、ハワイの未来を守る活動に関与していただくことこそ、新しい観光のあり方です。
ハワイでは、観光客が環境保護や文化継承に貢献できる機会も数多く提供しています。例えばメイドインハワイ製品や地元産の食品を積極的に購入することで、ハワイの文化を支えることができます。


もう一歩進んだ関わり方に興味があれば、ハワイのボランツーリズムもおすすめ。植樹をする際にハイキングをしながら固有種を学んだり、ビーチクリーンアップをしながら地元団体から海との関わりについて学んだりと、活動とツアーが一緒になっているものも多々あります。ハワイで開催されるイベントやフェスティバル、歴史散策ツアーに参加すれば、ハワイをより深く知ることができるでしょう。
観光の方には、単なるリゾート滞在ではなく、持続可能な社会づくりに貢献する一員となって楽しんでいただけたら嬉しいですね。ハワイの再生型観光の方向転換によりさらに奥深い地元コミュニティとつながった現地体験プログラムが増えていくことを期待しています。
Access to moment DIGITAL moment DIGITAL へのアクセス
認証後のMYページから、デジタルブック全文や、
レクサスカード会員さま限定コンテンツをご覧いただけます。
マイページ認証はこちら※本サービスのご利用は、個人カード会員さまとなります。
ログイン後、moment DIGITALのリンクまたはバナーをクリックください。
 ※バナーイメージ
※バナーイメージ