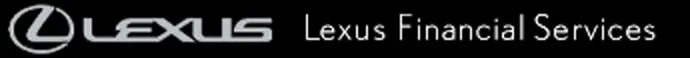日本のものづくり
京都・丹後の米と水と時が育むふくよかな一滴。飯尾醸造が醸す至高の酢
天橋立をはじめ、美しい海・山の景観を有する丹後半島は京都からドライブするのにぴったりの場所。食の魅力にもあふれており、この京丹後に130年の伝統を守る「飯尾醸造」は京丹後の食を牽引する一軒だろう。美しい棚田で育まれる無農薬米を使い、古式製法で造られる飯尾醸造の酢は、トップシェフたちにも愛用者が多い。自社で米を栽培し、酢を醸す造り手は日本でただ一軒だ。ドライブがてら買いに行きたい、こだわり抜いた飯尾醸造の酢がどのように造られるのかその背景を探る。
Photo&movie:Tadahiko Nagata
Text&Edit:Misa Yamaji(B.EAT)
平安時代から続く酢の歴史
日本料理に欠かせない基本調味料“さしすせそ”のひとつでもある酢。
世界に視野を広げてみれば、酢は紀元前5000年ごろの古代バビロニアの記録に残っており、世界でも最古の調味料ともいわれている。
日本においても和食の文化に欠かせない調味料として長い間、日本人の食を支えてきた。
日本での酢の発祥については、4~5世紀ごろにまで遡る。酒造りとともに中国大陸から伝わった説が有力で、奈良時代の「万葉集」には酢を使った料理「なます」を詠んだ歌がある。また、平安時代の「延喜式」には米と米麹を使った酢の造り方の記載が見られる。

米酢が調味料として一般的になったのは江戸時代になってからだ。江戸中期には江戸前鮨のブームとともに赤酢も一気に広まった。
この赤酢の誕生には面白い話がある。江戸時代、米酢はまだまだ高価な調味料だった。
そこで、現在のミツカンの創業者にあたる中野又左衛門が清酒を絞ったあとの酒粕から造る、安価で美味しい粕酢を開発。甘みと風味が強く、独特のうまみがある酢は「赤酢」と呼ばれ、当時流行していた江戸前のにぎり鮨にこぞって使われるようになっていったのだ。
こうしてさまざまな酢の製法が全国各地に広まり、それとともに酢を使った料理もたくさん生まれていく。

そんな江戸時代から伝わる、古式製法で酢を造りつづけている蔵元が1893年に創業した飯尾醸造だ。
古式製法の酢は米から清酒を造り、そこに酢を混ぜ、酢酸菌を加えて、じっくりと寝かせて造る。ところが現在は大量生産が主流となり、このように時間がかかる伝統的な製法で造る蔵元は少なくなってしまった。
というのも、蔵で一からすべてを手がけようと思うと、人手も時間もコストもかかるからだ。
水にアルコールを添加し、工業的に作られた発酵しやすい酢酸菌を合わせれば短時間で大量の酢ができる。生産性を優先する技術が発達することで、昔ながらの製法で造るメリットがなくなっていった結果だった。

しかし飯尾醸造では、そうした世間に迎合することなく自社で無農薬の米を育て、酒を醸すところからの酢造りを続けている。できた清酒から酢を造り、通常よりも長い期間熟成して商品にする。

一般的な酢の造り方に比べ気が遠くなるような手間と時間がかかっているのだが、一体なぜそこまでこだわるのか。
疑問に思い、五代目の飯尾彰浩氏に理由をたずねると「それが、私たちが生き残る道だからです」と真っ直ぐに答えてくれた。

「効率を求めた酢を造っても大手には敵わない。無農薬の米を使い、昔ながらの製法で時間をかけて造る酢は、どこにもない味わいと風味があります。私たちの酢はどうしても高い値段になってしまいますが、こうした品質に納得いただける方に買っていただくことで、商売が成り立っています」と続ける。
実際、名だたる天ぷら屋や鮨屋の店主から、その味に魅了され飯尾醸造の酢を愛用していると聞くことも多い。特に赤酢(一般販売していない)は、高級鮨屋の酢飯に使いたいと問い合わせも多く入るそう。しかし希望をもらっても、数が少ないため新規のお客さまにはなかなか販売できないのだという。

実は、飯尾醸造が酒をほかから買うのではなく、自社で醸す理由はこの赤酢を造るためでもある。
先に述べたが、赤酢は酒粕から造られる。酒粕で造る酢はほんのりと甘くうまみがあり丸いのが特徴だが、飯尾醸造では酒粕を最低10年寝かしたもので醸造。長期熟成することで独特の風味とうまみが生まれるのだ。
取材時、2011年の酒粕を見せてもらったが、長い時間をかけて小豆色に変わった酒粕からは、甘くて熟れた果物のようなよい香りがした。こうして時が育てた酒粕が原料だからこそ、通常とは違う複雑なうまみとまろやかな酸味の酢になっていく。
時間が酢の美味しさを引き出す
赤酢だけでなく、飯尾醸造を代表とする米酢「純米富士酢」も「富士酢プレミアム」も通常の酢よりも時間をかけて造られる。

飯尾醸造では、醸した酒と仕込み水と酢を混ぜてタンクに入れ、“酢酸菌膜”を浮かべて自然発酵を待つ「静置発酵」で酢を造る。つまり、人の力を極力加えず、菌の力でじっくりと発酵させていくのだ。
この“酢酸菌膜”は、酢を造る際に液面に湯葉のように張る膜のこと。この菌膜が液面の表面にびっしり張ってから酢酸発酵が始まる。

材料となる酒と水と酢を混ぜたタンクには、すでに発酵が始まっているタンクの菌膜をすくいとって浮かべ、発酵を促す。
そのままの状態で80日から120日の間、静かに発酵をさせるとアルコールが分解され酢になっていく。ちなみにこの酢酸菌、130年以上前の創業時から受け継いできたものだというから驚きだ。
飯尾醸造の酢の味は、この地の米と水とそして酢酸菌なしでは造れない。まさに土地と歴史が育んできた味といえるだろう。

そして発酵が終了したら、2カ月に一度タンクの移し替えを繰り返しながら240日から300日熟成される。この造り方も飯尾醸造の特徴といえるだろう。
飯尾氏によると「2カ月に一度、空気を含ませて熟成させることが大切なんですね。このひと手間で酢がまろやかになるんです」とのこと。

菌の力でゆっくり発酵させ、さらに熟成をさせた酢は複雑さがあって酸味の尖った感じがない。飯尾醸造を代表する「富士酢」も「富士酢プレミアム」もまったく同じ製法だが、「富士酢プレミアム」は使う米の量が「富士酢」よりも多く、企業秘密の製法によりさらにまろやかに仕上がっている。

さて、飯尾醸造の酢には、無農薬の米が欠かせない。なぜ無農薬でなければならないのか。
無農薬の米を使うことを決めたのは三代目の飯尾氏の祖父、飯尾輝之助氏だ。時代は高度成長期、強い農薬が使われていた時代だ。里山の生き物がいなくなっていったことに危機感を感じた輝之助氏は、宮津の農家に無農薬で米を作ってほしいと頼み込んだのだという。
以来、飯尾醸造ではずっと無農薬の地元の米で酢を造ってきた。手間もかかるが自社で水田を持ち、米作りにも携わっている。
「本当は誰かにお願いできるのならお願いしたいです。自分たちで米を作る理由は二つあります。ひとつは里山の風景をなくしたくないということ。二つ目は新しい農法や品種にチャレンジし、それを伝えることで契約農家の方の役に立ちたいと思っているからです」と飯尾氏はその理由を語る。

「富士酢」を試飲させてもらって、その複雑さと優しさが溶け込んだ味に、丹後に流れる雄大な時間を感じた。
そこに凝縮されているのは130年つないできた歴史と土地の恵みや風土。
天橋立など、丹後までドライブをしたなら、ぜひ立ち寄って試飲してほしい。
職人たちが丁寧に誠実に造る酢は、あなたの今までの“酢”のイメージを変えてしまうかもしれない。

飯尾醸造(酒蔵)
住所:京都府宮津市小田宿野373
電話番号:0772-25-0015
営業時間:平日 午前9時〜12時・午後1時〜5時(土曜・日曜・祝日休業)
URL:https://iio-jozo.co.jp/
Access to moment DIGITAL moment DIGITAL へのアクセス
認証後のMYページから、デジタルブック全文や、
レクサスカード会員さま限定コンテンツをご覧いただけます。
マイページ認証はこちら※本サービスのご利用は、個人カード会員さまとなります。
ログイン後、moment DIGITALのリンクまたはバナーをクリックください。
 ※バナーイメージ
※バナーイメージ