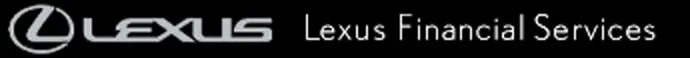TS CUBIC SHOPPING
トップシェフも惚れ込む「田野屋銀象」の“生きている”塩
料理好きならこだわりたい調味料“塩”。日本全国にさまざまな塩の生産者がいるが、今回紹介するのは高知県・土佐で作られる希少な完全天日塩。自然の力と塩杜氏の技術で作る塩はまろやかで、食材の味をぐっと引き出してくれる。そのため自らの料理に使いたいと料理人たちからのオーダーもあとを絶たない。太陽と風と毎日の手入れだけで40種以上の塩を作る職人・田野屋銀象氏の塩作りを取材した。
Photo:Tadahiko Nagata
Edit&Text:Misa Yamaji(B.EAT)
日本でも希少な「完全天日塩」
料理好きなら、キッチンに塩を何種類か常備している人も多いだろう。
世界にはさまざまな塩があるが、今は日本各地でもそれぞれ個性ある塩が作られている。中でも高知県は、火を使わず完全に太陽の力だけで塩を作る希少な“完全天日塩”の代表的な産地である。

今、この高知県の完全天日塩にシェフたちがアツイ視線を注いでいる。
というのも、実は日本での完全天日塩の歴史は浅く、ここ10年ほどでようやく生産者が少しずつ増え、手に入れることができるようになったのだ。
本題に入る前に、少し塩の製法と歴史について説明をしたい。
火を使わずに太陽と風だけで作る「完全天日塩」は、もともと晴天が多く乾燥した国での伝統的な塩の作り方である。有名どころでいえば、フランス・ブルターニュの“ゲランドの塩”などがそうだ。
しかし湿度が高く、年中雨の降る日本ではこうした製法は困難だった。そのため、日本の伝統的な塩作りといえば塩田で海水を濃縮し、その濃縮した海水を煮詰めて塩にする「揚浜式塩田」や「入浜式塩田」が主流だった。


そんな日本で完全天日塩が少しずつ作られるようになったのは、約30年前のこと。
1997年の塩専売制度が廃止となり、昔ながらの製法を復活させたり、新たな製法を開発するなど、特色ある自然海塩作りが全国各地で行われるようになった流れからだった。
高知県・土佐でもこの頃から完全天日塩作りが広がっていった。日差しが非常に強く、豊かな海を持つ土佐は天日塩作りに適した環境だったこともあり、同時多発的に方向性の違う業者が自然発生した。
その中から日本全国に名前が知れ渡る業者が現れ、近年はそこに若い職人たちが参入。それぞれが個性的な塩を生産し、いわば“「完全天日塩」の聖地”として、新しい産業となりつつあるのだ。

世界初、地下海水から作る天日塩
今回取材をした塩職人、田野屋銀象氏も、そんな若い職人の一人だ。現在31歳。土佐の天日塩の名を全国区にした塩職人・田野屋塩二郎氏の一番弟子だった人物だ。
今は新居海岸のそばに自社の工房を持ち、塩作りをして4年目になる。
天日塩を作る職人はほかにもいるが、銀象氏の作る塩の最大の特徴は、地下から湧き出てくる「地下海水」を原料としていることだろう。

砂地から滲み出た海水は、自然の濾過装置を通したかのようにクリアで不純物が少ない。しかも近くの清流“仁淀川”の水も少し混じることから、ミネラルは非常に豊富。
こうした地下海水が湧き出る場所は非常に珍しく、それを使った塩作りをしているのは世界でも銀象氏だけなのだという。
「実はこの地下海水との出合いは偶然の出来事でした。独立するにあたり日照時間が長く風が適度に吹き、きれいな海水がある場所を探して今の場所を見つけました。けれど、海岸線の目の前には県道があり、海水を直接汲み上げるのが難しい。近所の人にそんな話をしたら、“このあたりは地中に海水が滲み出ているんだよ。昔はその水を井戸で汲み上げて、釣り餌のゴカイを養殖する業者がいた。その井戸が使えるんじゃないかな”と教えてくれたんです」

銀象氏は驚き、そのあたりの土地を調べてみると、まさに神様が用意してくれていたかのように、海水が湧き出る井戸が残っている土地があった。
「ここで塩を作ろう」。心は決まった。
この海水に出合ったことで“このきれいな地下海水を活かし、手間と時間をかけて塩の力を引き出すような深い塩作りをしていこう”と、目指す方向性もはっきりと見えたと話す。
シンプルな調味料だからこそ、深く突き詰めたい
完全天日塩の作り方は実にシンプルだ。
まず、井戸から汲み上げた海水を風が通り抜ける小屋で雨のように上から垂らし、斜めになっている床の上に流す。落ちていく海水の水分を太陽の熱と風とで少しずつ蒸発させることを繰り返し、濃度の高い塩水を作っていく。

4%から5%の濃度まで濃縮したら、別棟のビニールハウスのような建物の中にある木の箱の中に塩水を満たす。
そこから、太陽の光と風を当てながら、塩水を手で混ぜて塩の結晶を作っていくのだ。

天日塩作りの仕組みはどの職人もほぼ同じなのに、仕上がりが職人ごとでまるで違うのが面白いところだ。
しかも銀象氏は、同じ原料、かつシンプルな工程のみで常時40種類以上もの塩を作るのだという。

「塩の味は、ミネラルバランスと結晶の溶け方で決まります。溶け方に大きく影響する要素が塩の形状と硬さです。それをどう作るかは、作る人の感性によるものが大きいですね。10人の職人がいれば10とおりの塩になるんです」と銀象氏。
塩に含まれるマグネシウムやカルシウム、カリウムの含有量が変わることで、味の印象も変化。また、結晶の大きさや形も重要だ。塩が口の中でゆっくりと溶けると、まろやかに感じられ、急速に溶けると、塩味が強く感じられるのだという。

「微妙な風の当て方、日光の当て方、かき混ぜ方などを考えながら、ミネラルのバランスと結晶の大きさや形をサポートし育てていきます。そうすると、まったく違う味わいの塩が何千とおりもの組み合わせでできるんですよ」と教えてくれた。

こうした天日塩の特性を活かし、銀象氏はシェフたちのリクエストに合わせてオートクチュールで塩を作っている。自身も食べることが大好きということもあり、一緒に味をイメージしながら形やミネラルバランスを微調整して作っていく作業はとても楽しいのだそうだ。
実際さまざまな箱の中を見せてもらったが、一般的な細かい塩、粗塩、サイコロ状の大きな粒の塩からフレーク状の塩、さらにはピラミッド型までさまざまな塩が育っている。


同じタイミングで注がれた塩水が同じ室温の中にあるのに、でき上がりがまるで違うのが面白い。銀象氏の手と意識が塩水を自在にあやつり、時間をかけて美しい彫刻を作っているかのようなのだ。

食材に秘められた力を引き出す3種の塩
銀象氏が一般に販売している塩に、野菜用の細かい粒、魚用の中粒、肉用の大きめの粒の3種がある。

試食をさせてもらったが、どれも丸みがあってうまみが濃い。いわゆる“しょっぱさ”が前面に出てこないので、清らかな海水のまろやかさを感じる。にがり由来のえぐみや苦味が少ないのも特徴だ。また大きさや形状で味の感じ方が違うというのは、食べ比べるとよくわかる。

野菜用は、合わせる食材全体にすーっと馴染む。魚用は中サイズの粒子で焼き魚にするときにかけると、魚のうまみを引き出し、甘みが感じられるような仕上がりに。肉用は、肉を焼いて、皿に盛りつけたあとに乗せて一緒に食べるイメージだ。こうすることで、肉汁が塩と合わさり、口の中でまるで出汁のようなうまみとなる。
いずれもただの調味料では終わらない。味を付けると同時に食材の味をぐっと底上げする力強さを兼ね備えている。その味わいの広がり方を一度知ってしまうと、ただ味付けに使うのではなく、使うタイミングや量にまでこだわっていろいろと試したくなってしまう。
太陽と情熱を結晶させた天日塩
完全天日塩の生産は、夏場は60度を超えるハウスに長時間こもらなければいけない大変な仕事だ。

さらに、“収穫”までの時間が長いのも大変なのだという。銀象氏は「塩になるまで夏場は2カ月、冬場は3カ月かかります。その間毎日ずっと手を入れなければいけませんから。でも思ったとおりの塩ができると本当に嬉しいです」と顔をほころばせる。

そんな過酷な仕事を、なぜここまで夢中に突き詰められるのか。
「僕、高校時代にパンクバンドをやっていたんですね。当時、舞台でギターを叩き壊しちゃって新しいものを買うためにアルバイトをしたのが、たまたま師匠の塩工房だったんです。そこから塩作りにはまってしまって、こうして今塩を作っています」と笑う銀象氏。そんな笑顔を見て、神様はしかるべきところにしかるべき人を導いたのかもしれないと思った。
銀象氏の作る小さな一粒一粒の塩には、清らかな土佐の海と太陽、そして長い時間と、銀象氏の情熱がギュッと詰まっている。
今回ご紹介した「田野屋銀象」については、以下リンクよりご購入いただけます。
TS CUBIC SHOPPINGサイトでは、ほかにも多くの商品を取り扱っております。
Access to moment DIGITAL moment DIGITAL へのアクセス
認証後のMYページから、デジタルブック全文や、
レクサスカード会員さま限定コンテンツをご覧いただけます。
マイページ認証はこちら※本サービスのご利用は、個人カード会員さまとなります。
ログイン後、moment DIGITALのリンクまたはバナーをクリックください。
 ※バナーイメージ
※バナーイメージ